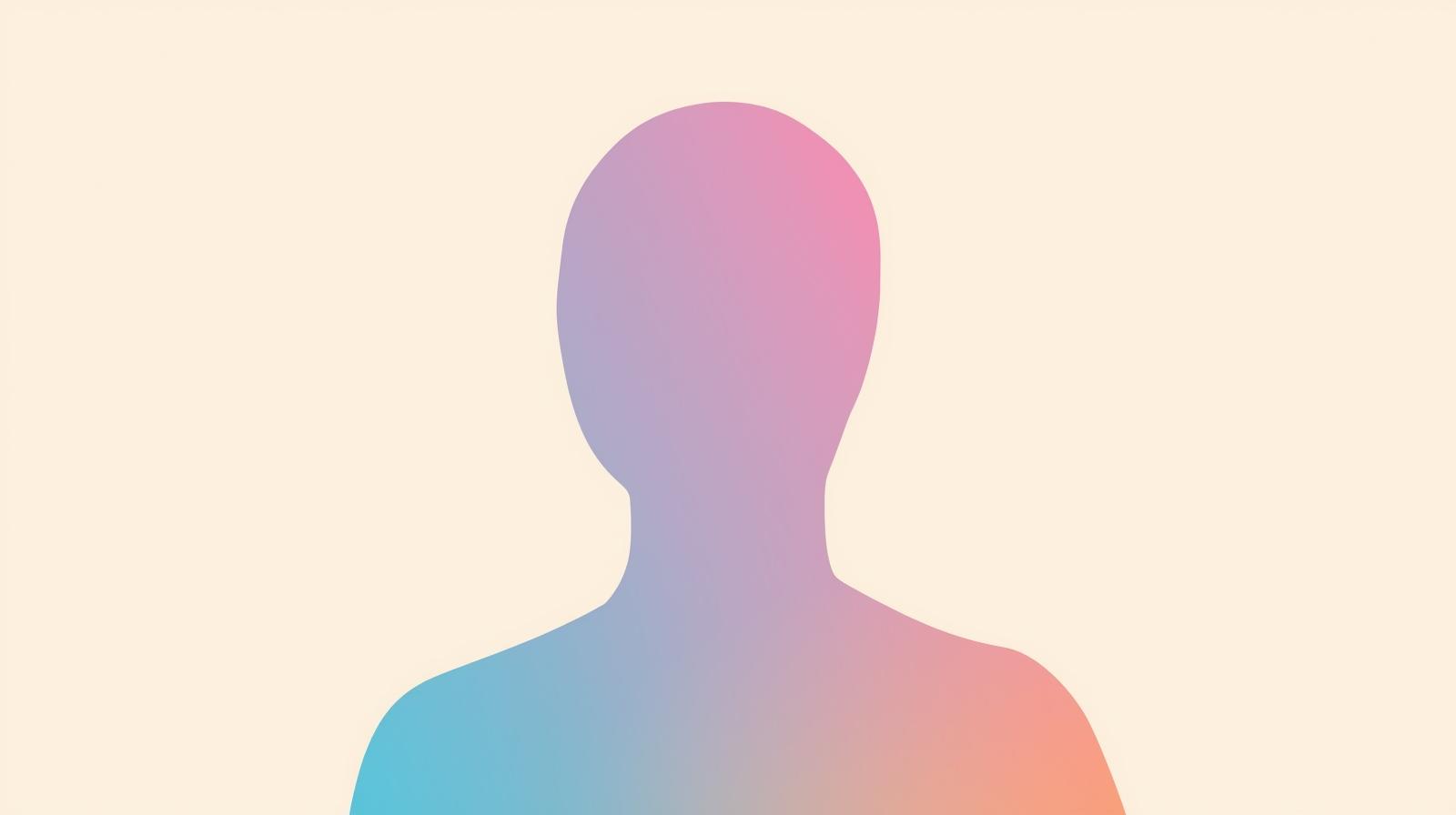「出た、“関係者”。」
ニュースを読んでいると、必ず登場します。
「関係者によると」
「制作スタッフの話では」
「芸能関係者が明かした」
——誰?
名前も肩書きも出てこないのに、なぜか“絶対的な説得力”を帯びている。
この「関係者」という存在、実はニュース界の都合のいい神様のようなものです。
現れた瞬間に、すべての主張が「第三者の声」っぽく聞こえる。
でも、その“声”は本当に存在しているのでしょうか。
🔍 「関係者」はどう生まれたのか
「関係者によると」——
この表現のルーツは、政治・外交報道における安全弁です。
1950〜70年代の欧米報道では、
国家機密や汚職を内部から暴く内部告発者(whistleblower)を守る必要がありました。
そのため、記者たちは「匿名を条件に取材に応じた情報源」を“official source”や“government official”と呼び、
身元を隠したまま社会に重要な情報を伝える手法を確立しました。
1971年のペンタゴン・ペーパーズ事件や、
1970年代のウォーターゲート事件など、
匿名情報源の保護が国家の不正を暴いた象徴的な事例です。。
この原則は後に、
SPJ(Society of Professional Journalists)倫理規定 にも明記されました。
“Identify sources whenever feasible. The public is entitled to as much information as possible to judge the reliability and motivations of sources.”
「可能な限り情報源を特定し、読者がその信頼性と動機を判断できるようにすべきである。」
つまり、「匿名」は記者のためではなく、社会のためにリスクを負って告発する人を守るための仕組み。
これが「関係者」という言葉の出発点でした。
🧠 いつから“腹話術”になったのか
時代が進むにつれて、報道現場ではこの匿名形式が“便利な書き方”として定着していきました。
とくにエンタメや芸能記事では、実名を出せない裏話や感想を添えるために、
「関係者談」が記者の意見の代弁者として使われるようになります。
「制作関係者によると、最近の番組内容に懸念がある」
と書けば、記者の主張を“他人の声”として書ける。
これが、報道の腹話術構造の始まりです。
UNESCO報道倫理ガイドライン ではこう警告しています。
「匿名は例外であり、乱用は報道の信頼性を損なう。」
匿名のまま語る“関係者”は、真実を守る盾から、責任をぼかす霧へと変わっていったのです。
🕵️♀️ 「都合のいい匿名」が生み出す構造的問題
匿名発言には2つの側面があります。
1️⃣ 腹話術効果
記者自身の主張を「関係者の声」として出すことで、中立を装える。
実際には“誰も言っていないこと”を“誰かが言ったこと”に変えられる。
2️⃣ 安全装置効果
もし情報が間違っていても、“関係者”という曖昧なクッションが責任を吸収してくれる。
結果、「誰も間違っていない構造」が完成する。
この“安全な腹話術”は、報道倫理の観点からみても非常に危うい。
IFJ(国際ジャーナリスト連盟)倫理憲章 は明言します。
「ジャーナリストは、情報源を可能な限り明示し、匿名を用いる場合はその正当な理由を説明しなければならない。」
しかし、現実のエンタメ記事では、匿名の声が説明もないまま、事実を飾る装飾として多用されています。
📚 歴史は“社会を守る匿名”、今は“物語を支える匿名”?
1970年代に匿名情報源が公共の利益(public interest)のために使われた一方、
現代の報道では“物語の演出”として機能する場面が増えています。
・「現場では戸惑いの声も」
・「ファンの間では波紋が広がっている」
・「関係者によると、〜が決定的だった」
これらの文は、読者に「みんながそう言っている」という錯覚を与え、
ニュースを社会的合意のように見せかける。
まさに、“匿名の集合意識”を人工的に作り出すレトリックです。
🌻 まとめ:匿名は悪じゃない。でも、乱用は信頼を腐らせる。
匿名の取材源が悪いわけではありません。
本来は、危険を冒して真実を告げる人を守るための仕組みでした。
でも、守るべき誰かがいないなら、それはただの逃げ場所です。
“関係者”の声を借りて断定する記事は、もう報道ではなく演出になってしまう。
ニュースを読むときは、
「この“関係者”って、誰の声だろう?」と一度立ち止まるだけでいい。
——煙の向こうに、本当の声が見えるかもしれません。