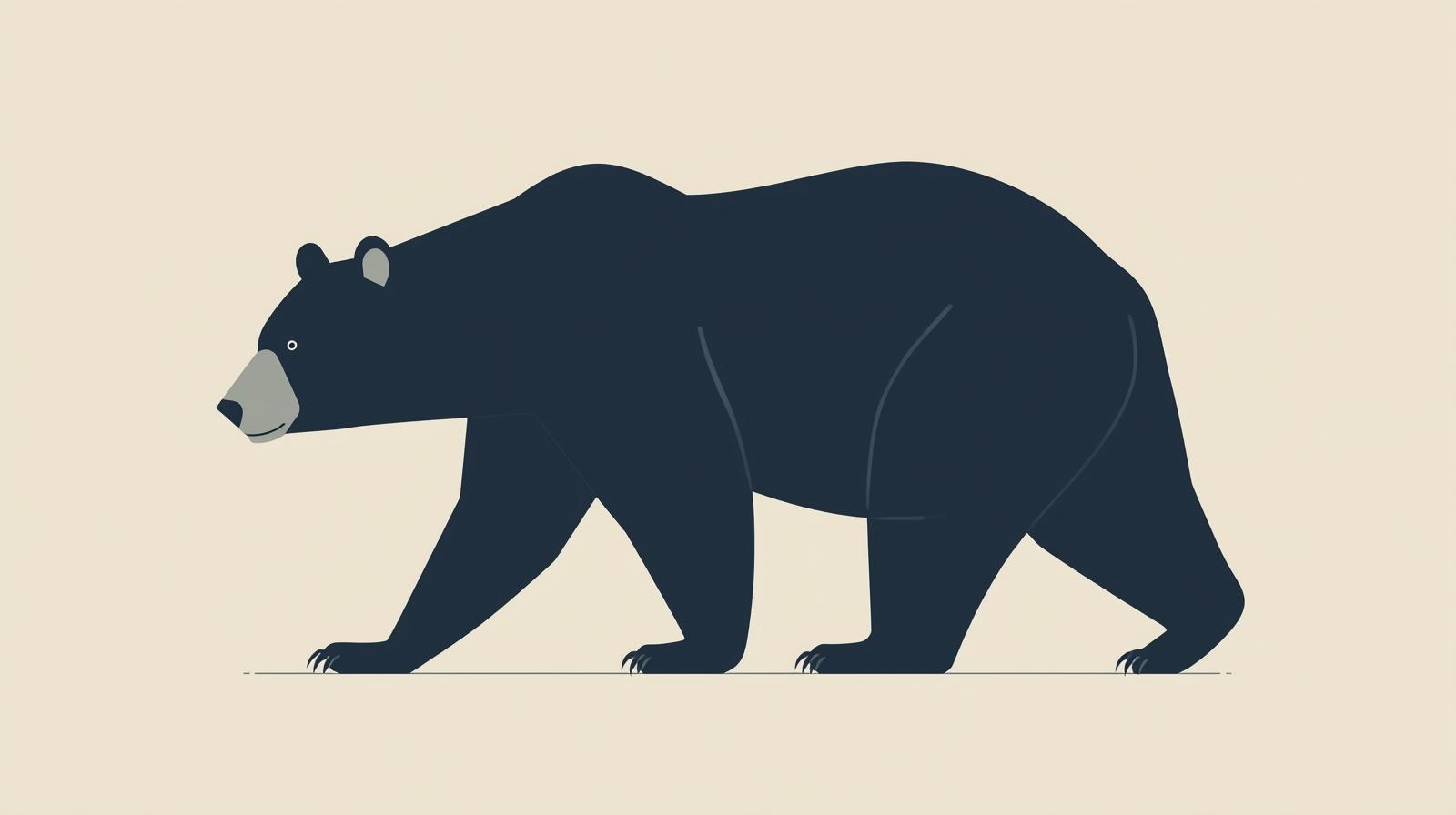🌙 「かわいそう」で始まる誤解を招く記事構成
《駆除するなんて熊がかわいそう酷すぎる。》
《森に返してあげて》
《ハンターに天罰が下りますように》
Yahoo!ニュースに掲載された記事は、こんなSNS投稿から始まります。
そのすぐ下に、宇多田ヒカルさんの写真。
そして本文にはこう書かれています。
「全国各地で多発しているクマ被害は…」
「ネット上でも『クマがかわいそう』とする声が根強く聞こえ——」
文を読む流れの中で、読者は“宇多田ヒカル=かわいそう派の代表”という印象を受けてしまいます。
けれど、ここに登場するSNSの言葉は宇多田さんの発言ではありません。
まったく無関係な他人の投稿なのです。
🪞 宇多田さん本人が明かした「構成トリック」
宇多田さん自身が、Xでこう説明しています。
今日本で話題のクマ報道に乗っかって、私の昔の発言を引用してる週刊誌の記事が出てYahooなんかでも紹介されてるみたいで、見出しや内容読んだ人は私が「クマが可哀想で泣いてる」「ひどい!ハンターに天罰が下ればいい」なんておっかないこと言ってると思って批判的な意見がチラホラ届いてるんだけど…
— 宇多田ヒカル (@utadahikaru) November 4, 2025
「SNS上のランダムな人たちの過激な発言を、そうとは明記せずに私の写真の下に掲載、そのまま私の話やほんとの引用が始まる構成だと判明。
そんな手があるんかい😂本人の私でも騙されそうになったわ😂」
確かに記事を読むと、「“駆除するな”と泣く人たち」の近くに、彼女の写真。
次に出てくるのが「宇多田も当時のツイッターで——」。
まるで同じ主語の発言のように見える構成です。
“本人ですら誤解しかけた構成”。
ここに、表現の倫理が問われます。
SmokeOutではこれを「構成による誤認(Framing by Juxtaposition)」と呼びます。
意図的に切り抜いた発言ではなく、並べ方だけで印象を作る手法です。
🧩 「本人の言葉」はどこにあったのか
記事の中には、宇多田さんの過去の実際の投稿も引用されています。
2010年、クマの放獣をめぐる議論が起きたとき、宇多田さんはこう書いたとあります。
「クマを森へ返すための予算を管理してる機関があるなら寄付したいな。ちょっくら調べるぞ!」
「射殺よりは捕獲して森へ返すほうがまだいい。今すぐできることもやりつつ、環境問題も勉強したいです。」
これは“極端な擁護”ではなく、共存を模索する姿勢でした。
その後、2021年の『読売KODOMO新聞』では、
「本物のクマはとんでもなく強く、人間にとって脅威でもある生き物」
とコメントしたとあり、単なる“かわいそう論”ではなく、人間と自然の共存の難しさを語っています。
つまり彼女の発言には一貫して思考の深化があり、感情的でも過激でも単純でもありません。
🧠 「かわいそう」と「脅威」の間にあるもの
それでも記事はこうまとめています。
「かわいそう論が出るのは、長年にわたる“クマ=かわいい”が刷り込まれているのかな、と」
ここで注目すべきは、「かわいそう論が出る」という主張に、具体的な根拠が示されていないことです。
記事冒頭のSNS投稿も、誰が・いつ・どこで発したか不明。母数も提示されていません。
それなのに、この根拠不明の論の前後に、宇多田さんのエピソードが配置されています。
1. 「かわいそう論が根強く聞こえる」(根拠不明)
↓
2. 前後で宇多田ヒカルさんのエピソードや過去の発言(文脈を無視)の紹介
↓
3. 「“クマ=かわいい”が刷り込まれている」(根拠不明)
この構成から読者の一部は:
「かわいそう論という世論がある(根拠不明)」
「その一因は、宇多田ヒカルの『ぼくはくま』や、発言にあるのでは?」
という印象を受けてしまうかもしれません。
ただし、あくまで記事はそうとは明言していません。
だからこそ、批判されても「そんなこと言っていない」と逃げられる。
根拠のない論証を、特定の人物と結びつける。
しかも、明言せずに暗示だけで。
これが、最もタチの悪い手法です。
本人の投稿には、ハンターや行政を責める言葉は一切ありません。
改めて本人の発言を確認しましょう。
「本物のクマはとんでもなく強く、人間にとって脅威でもある生き物ですが、こんなに『かわいい』と思えるのはなぜでしょう?」
感傷ではなく、探求と葛藤。
それを「かわいそう論」と暗示的に結びつけるのは、意図の有無に関わらず、読者を誤解させるおそれがあります。
💬 「本人でも騙される」時代に
宇多田さんのX投稿の最後の一言が印象的です。
「ネットや週刊誌の情報を鵜呑みにしてるのは少数派だと信じてるけど、にしてもこういう世間の憤りを関係ない有名人に向けようとするのやめてほしい😞」
これは、今の情報環境全体へのメッセージです。
ファクトチェックではなく、“表現チェック”が求められている。
ファクトチェックは「事実が正しいか」を確かめる。
でも、多くの誤解は“事実”ではなく、“構成”の中に埋め込まれる。
記事の中で、引用は正しい。数字も正しい。(かもしれない)
それでも、順番・語尾・見出しの“置き方”ひとつで意味は反転してしまう。
この“構成の力”を監視する視点が、いまのメディア環境に決定的に欠けている。
だからこそ、SmokeOutは“ファクトの真偽”ではなく、“表現の意図”をチェックする。
それが「文脈の正義」を守る第一歩だと考えています。
誰かの怒りの矛先が、まったく関係のない人に向かう——
その連鎖を断つには、「言葉の配置」まで検証するリテラシーが必要です。
🌱 「けんかはやだよ」
- 無関係なSNS投稿と本人の言葉を並べない
- “主語の透明性”を守る
- 「かわいそう」も「脅威」も、どちらも現実の一部
記事の最後にある
『ぼくはくま』の歌詞にある、【けんかはやだよ】は誰に向けての呼びかけだったのだろうか。
これはニュースを作る人たちが噛み締めるべき言葉だと思います。