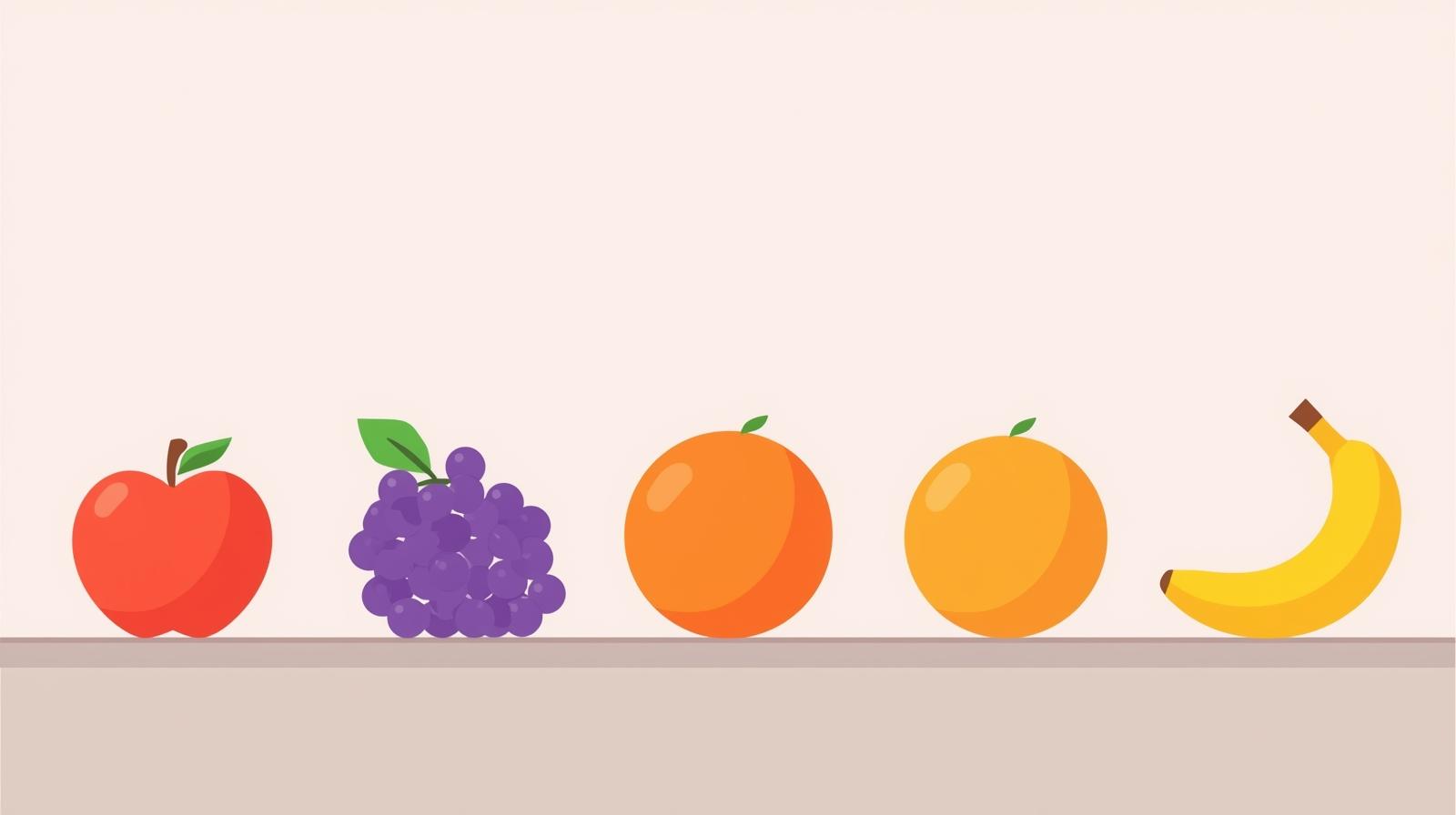🎤 何が起きたの?
10月19日に予定されていたイベント「SAMURAI SONIC」。
公式アカウントが「FRUITS ZIPPER出演決定!」と大々的に発表しました。
…でも実際は、主催が「自社社員を名乗る人物」と効力のない契約を結んでいただけ。
FRUITS ZIPPER側はそもそも出演調整なんてしていなかったのです。
事務所はすぐに公式で謝罪。
「ファンの皆様におかれましては混乱を招いてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます」
🤔 でも見出しを見てみると…
「FRUITS ZIPPER 『深くお詫び申し上げます』効力持たない出演契約が締結」
──え、まるでグループ本人たちが怪しい契約をしたみたいに読めませんか?
実際の責任は主催側。
FRUITS ZIPPERはただ巻き込まれた“被害者”に近い立場です。
🔍 論理のすり替え
A:主催が契約トラブル
→ B:公式が出演を発表
→ C:公式と事務所が「出演しません」と謝罪
👉 この流れを「謝罪=FRUITS ZIPPERが悪い」と見せるのは主語のすり替え。
記事本文を読むと誰の責任かは分かるけれど、見出しだけ見た人には誤解が残りやすい。
国際的な報道ガイドラインでもこうした切り取りはアウト寄りです。
たとえば SPJ倫理綱領 は「文脈を示せ」と明記してますし、UNESCOのハンドブック も「責任主体をぼかすな」と警告しています。
🪄 見出しのリライト案
元:
FRUITS ZIPPER 「深くお詫び申し上げます」効力持たない出演契約が締結
改善:
- 「主催の契約トラブルで混乱 FRUITS ZIPPERは出演せず」
- 「FRUITS ZIPPER巻き込まれ イベント側の誤契約で不参加に」
- 「出演決定は誤発表 FRUITS ZIPPER側は冷静に説明」
❤️ まとめ
FRUITS ZIPPERは「被害者」であって「加害者」じゃない。
それなのに記事は「謝罪」というワードだけを拡大し、彼女たちが何かやらかしたように読ませてしまう。
ファンが欲しいのは「今回の経緯の透明性」と「本人たちに責任がない安心感」。
メディアが“謝罪フレーズ”を切り貼りしてドラマを作るたび、アーティストへの信頼を無駄に削ってしまうのではないでしょうか。