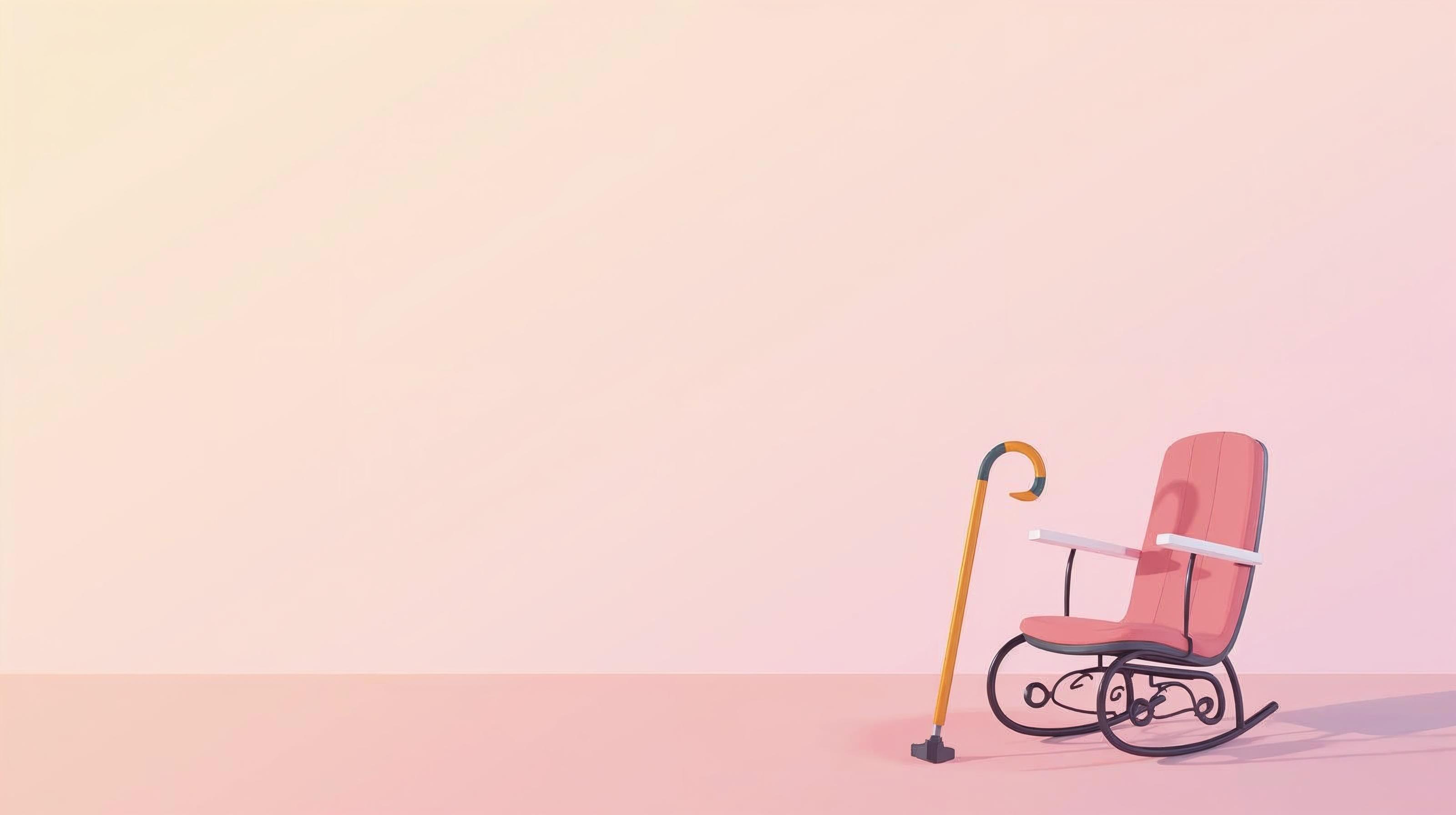📣 この記事、読んでモヤっとしませんでしたか?
粗品さんに向けられた「若年性老害」という言葉。強烈なインパクトがあります。
でも、そのインパクトが、どんな“書き方”で生まれていたのか、じっくり見てみたことはありますか?
SmokeOutでは、国際基準(UNESCO・IFJ等)と論理・レトリック技法に基づいて、記事の“中身や事実の正誤”ではなく“伝え方”のリスクを可視化しています。
今回分析したのは、2025年7月31日付・マネー現代の記事:
👉 菊池風磨や木村拓哉に苦言…霜降り明星・粗品はもはや「若年性老害」か、主張する「芸人至上主義」の大きな矛盾点
🧨「もはや老害」って、どういう前提ですか?
記事冒頭の見出しがこちら:
霜降り明星・粗品はもはや「若年性老害」か
「か?」と疑問形にしていても、「もはや」という言葉がほぼ断定のような効果を持ちます。
これは、表現リスクの中でもとくに強力な「人格ラベリング(名辞的決めつけ)」に該当します。
🔖 ラベリングとは?
特定の言葉で人物を定義づけ、以降の解釈をそのレッテルに縛る手法。
「老害」という語には、年齢や価値の低下を暗示する差別的ニュアンスが含まれます。さらに「若年性」と組み合わせた造語にすることで、皮肉と攻撃性を増幅しています。
国際的な報道倫理(UNESCO/IFJ など)では、人格に関わる蔑称や差別的ニュアンスを含む語の安易な使用を避けるよう求めています。特に「老害」という言葉は、年齢に基づく価値低下を暗示する年齢差別的ニュアンスを持ち、新造語「若年性老害」によって刺激度をさらに上げています。これは読者の冷静な判断をにぶらせる高リスク表現と言えるでしょう。
国際基準(原文引用とリンク):
Global Charter of Ethics for Journalists(ジャーナリストのための世界倫理憲章)
“Journalists shall… avoid facilitating the spread of discrimination…”
(差別・偏見の助長を避ける)世界人権宣言 第1条
"すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である。"
🪜 A→B→Cの論理が、途中でワープしてる
記事構造をざっくり分解するとこうなります:
- A(主張の提示)
- 「俺は芸人至上主義や」「芸人にリスペクトのないヤツは警告」
(※芸人至上主義=芸人を最も尊重すべきという価値観)
- 「俺は芸人至上主義や」「芸人にリスペクトのないヤツは警告」
- B(反証的エピソードの列挙)
- 木村拓哉さんへの“噛みつき”発言
- King & Prince への「いまの状態のキンプリ、誰が見るねん」
- 宮迫博之さんを「宮迫」「アイツ」と呼ぶ 等
- C(人格ラベリング)
「粗品は若年性老害」
おや? その飛躍、見逃していませんか?
Bのエピソード(言動の矛盾)からCの人格断定(老害認定)へのジャンプには論理的な根拠が不足しています。
ここでのポイントは、Bの具体例は「態度の不一致」を論じる材料にはなりますが、Cの人格ラベルに直接つなげるには根拠が不足しているということです。
論理・レトリック技法では、過度の一般化(overgeneralization:一部の事例を全体に当てはめる誤り)+本質化(essentializing:ある特徴をその人の本質とみなす手法) の複合といえます。
該当する論理・レトリック技法(論理的誤謬):
- 過度の一般化(Overgeneralization)
一部の事例をもって全体の性格や本質を決めつける誤り。
- 本質化(Essentializing)
特定の行動や特徴を、その人物の本質的な性質として固定化する手法。
🧩 言葉の舞台裏:脚本はこう組まれていた
その他にも論理・レトリック技法が随所に使われています。
1. ラベリング(名辞的決めつけ)
- 「若年性老害」「主観至上主義者」など、強い人格ラベルを繰り返し使用。
→ 読者の印象が“固定”されてしまいます。
2. アド・ホミネム(人物攻撃)
- 該当箇所:「ただ単に利己的な「主観至上主義者」でしかないのです。」
- 判定理由:主張の妥当性ではなく人物そのものに矛先が向きます。(論点からの逸脱)本来は行為や意見の是非を論じるべきところを、発言の言い回しや呼び方を取り上げて、その人物像や礼節に欠ける印象を植え付ける手法で、議論の焦点を論点から人格へすり替える危険があります。国際報道倫理では、こうした人格的な断定は慎重に扱うよう求められます。
3. ストローマン(単純化・歪曲)
- 粗品さん:「芸人に敬意がないのはイヤだ」
- 記事側:「芸人以外を全否定してる!」
→ そんなこと、言ってません。「A(敬意を求める)」→「B(他者全否定)」へのジャンプは別物です。これは「ストローマン論法」と呼ばれ、相手の主張をわざと極端にして叩くレトリック技法です。原主張より強い(極端な)射程へ置き換え、批判しやすくしています。
4. 反復強化
- 該当箇所:記事中で「老害」関連の表現やネガティブな言い回しを複数回使用。
- 判定理由:同じ否定的語句や関連ニュアンスを繰り返すことで、読者の印象を強固にしています。これは論評というより、印象操作です。
5. 引用選択による印象形成(軽視的呼称の提示)
- 該当箇所(引用部分):〈「先輩じゃないっすよ、アイツ」〉
- 判定理由:軽視ニュアンスの強い呼称を選択・配列して提示することで、読者に人物像の印象を強める編集技法です。
🔎 ところで「ネットの声」って誰の声?
記事では「ネットではこうした声も」という文言が繰り返されますが、出典・件数・時期などの情報はゼロです。
これは、いわゆる「世論のような空気」を演出する常套手段。
SPJ(米ジャーナリスト協会)倫理指針
“Identify sources clearly. The public is entitled to as much information as possible…”
(情報源を明確にすること。読者は判断の材料を得る権利がある)
🪄 この記事タイトル、こう直した方が良いのでは?
現行:
菊池風磨や木村拓哉に苦言…霜降り明星・粗品はもはや「若年性老害」か、主張する「芸人至上主義」の大きな矛盾点
これは、強い印象ワード+疑問形で印象を押し付ける構造です。
💡 改善提案(例):
- 粗品さんの「芸人への敬意」発言、その整合性を検証する
- 「芸人至上主義」発言の背景と、過去との矛盾は?
- 粗品さんの言動、どこまで理念と一致している?
主語を「人物」から「発言・文脈」に移すことで、読者が冷静に判断できます。
記者ご自身の思いを誤解なく主張するためには、このような見出しに変えてみてはいかがでしょうか。
人物の本質断定語は用いず、主語を発言や文脈に置き、読者の解釈に余白を残しましょう。
🧯最後に:言葉の火は、誰がつけたのか?
粗品さんの発言に、矛盾や選択的適用があるという批判は成立します。
でも、その指摘は論理で主張すればいい話です。
「若年性老害」というレッテルを貼るのは、もう別次元の話。
それは議論ではなく、印象操作という“演出”です。
🕊️ 表現の自由は守りたい。でも、それは「使い方」も含めて。
だから私たちは、火のないところに立った煙を見つめます。
言葉の力が暴走しないように。
誰かを守るために、誰かを傷つけないために。
——SmokeOut
憶測の“書き方”を、読み方でほどくために。