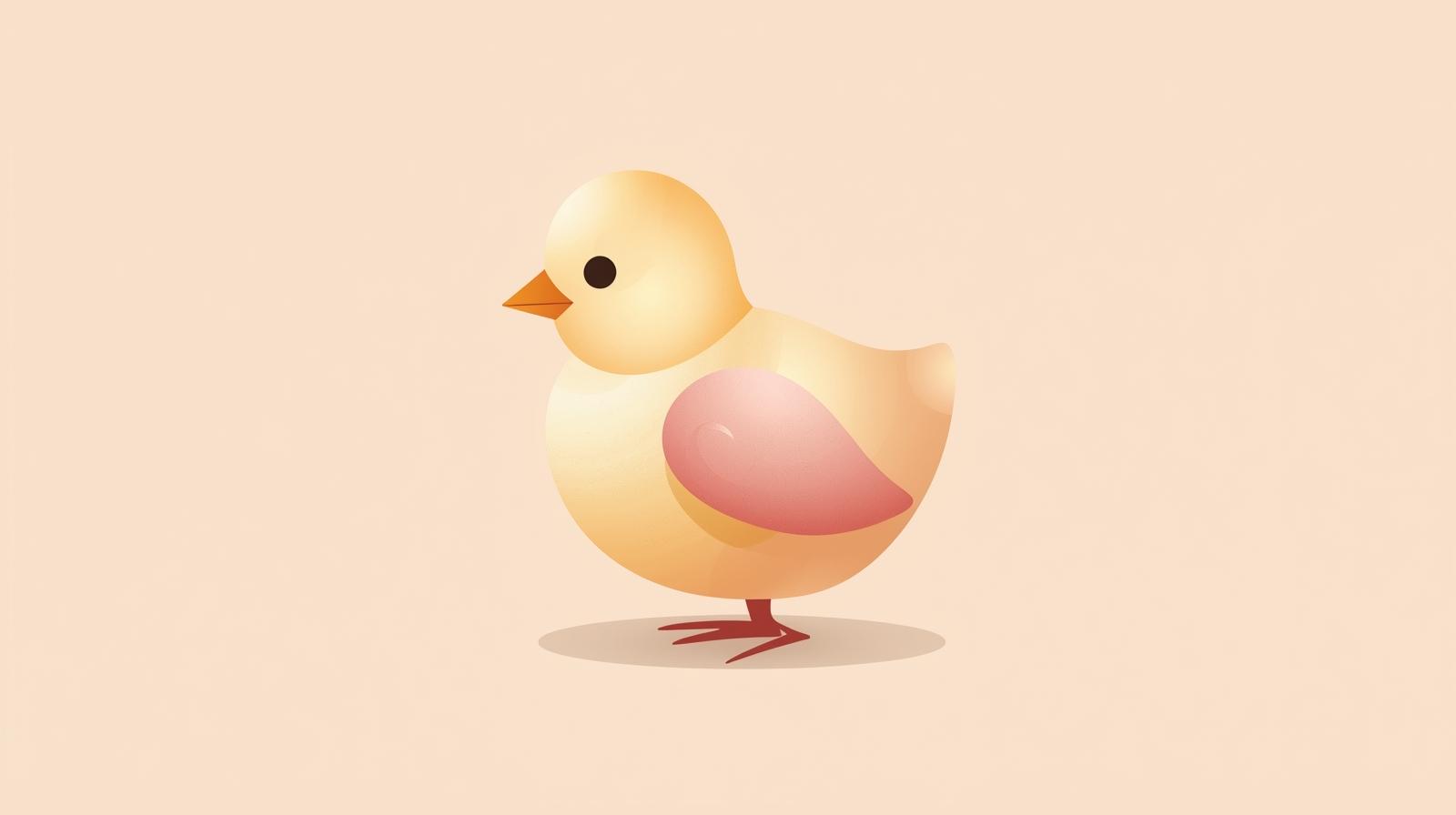🪞「棒立ち」から「ゴリ押し」へ —— 繰り返される“新人叩き”構文
「過剰供給なtimelesz篠塚大輝、事務所“ゴリ押し”疑惑に批判殺到」。
見出しからすでに、
- “過剰供給”
- “ゴリ押し”
- “批判殺到”
という三段階のネガティブ連鎖が仕込まれています。
しかも本文では、冒頭でいきなりこう説明されます。
《またtimelesz? フジはゴリ押しすぎ》
《ちょっと出すぎかな》
《この人が出る時はzipにしよう》
SNSの声が並び、そこから“物議を醸している”という流れをつくる。
少数の反応を冒頭に置くことで、読者に「すでに議論がある」と錯覚させます。
🧩 「プロ意識が足りない」という即断の罠
記事が“根拠”として持ち出したのは、10月のZIP!体操コーナーでの一件。
「Snow Manの阿部亮平さんが考案した体操で『シェー』の振り付けを間違え、棒立ちになった」
この「棒立ち」という言葉、過去の別の記事でも見出しにも使われていましたが、
あくまで、“棒立ち”は一瞬の切り抜きであり、人物像の全体を語るものではありません。
それでも記事がそれを“プロ意識が足りない”という文脈で扱うと、
読者は「棒立ち=怠慢」「新人=未熟」という連想を抱いてしまいます。
“Journalism should avoid speculative or sensational coverage of individual performance or appearance.”
「ジャーナリズムは、個人のパフォーマンスや外見に関して、憶測的・扇情的な報道を避けなければならない。」
🧩 無関係なミスと結びつける「論点のすり替え」
そもそも、この「棒立ち」のエピソードは、記事の主題である「事務所の“ゴリ押し”疑惑」と直接的な関係があるのでしょうか。
- 「ゴリ押し」とは、事務所の戦略や業界構造に対する疑惑です。
- 「棒立ち」とは、個人のパフォーマンスにおける一度きりのミスです。
両者に論理的な繋がりはありません。ではなぜ、記事はこのエピソードを重要であるかのように扱うのか。
「論点のすり替え」です。
本来議論すべきは「事務所のプッシュは本当に過剰か?」という構造的な問題です。
しかし記事は、「(こんなミスをする)未熟な彼が抜擢されるのは、やはり“ゴリ押し”だからだ」という感情的な納得を誘導している。
これは、「ミスをしない人間などいない」という普遍的な事実を無視し、
一度の失敗も許さない“不寛容さの構文(Intolerance Framing)”へとつながります。
新人であれベテランであれ、誰にでもミスはあります。
それを「プロ意識の欠如」と断罪する報道は、挑戦と成長の余地を社会から奪っていく。
🧠 「ゴリ押し」という言葉の構造
「そもそもtimeleszといえば今、各局を席巻中だ。」
「STARTO ENTERTAINMENT所属の別のグループファンから反感を買うかもしれません」
こうした一節には、「反感を買うかもしれない」という仮定の主語が隠れています。
つまり、実際に反感があったかどうかよりも、「反感があることにして書く」構文。
“ゴリ押し”という言葉は、誰かの主観的印象に基づく評価でありながら、あたかも“視聴者の総意”のように提示されています。
“Respect for the facts and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist.”
「事実と、真実を知る市民の権利を尊重することが、記者の第一の義務である。」
つまり、“反感があるかもしれない”という推測を事実のように書くことは、この原則に反して、読者の判断権を奪うことになります。
💬 SNSの「批判殺到」は、誰の代弁か
記事内で「批判殺到」とされている投稿は、実際には数件の引用にすぎません。
しかし、それが見出しに置かれると、まるで炎上しているかのような印象を生みます。
SNSの一部の感情を、メディアが“世論”として再構成する。
🌱 まとめ:叩くより、育てる目を
✓ 一瞬の映像で「棒立ち」と決めつけていない?
✓ “ゴリ押し”という印象で、成長の過程を消していない?
✓ 「批判殺到」は、実際にどれほどの数だった?
新人を“叩く対象”として消費する構造は、読者の無意識の中にも潜みます。
篠塚大輝さんは、まだキャリアが始まったばかり。
「慣れていない」を「未熟」と責めるより、「慣れていく」を見守る方が建設的ではないでしょうか。
報道がその変化を“異変”ではなく“成長”として伝えられる日。
それが、健全なエンタメ報道の第一歩です。